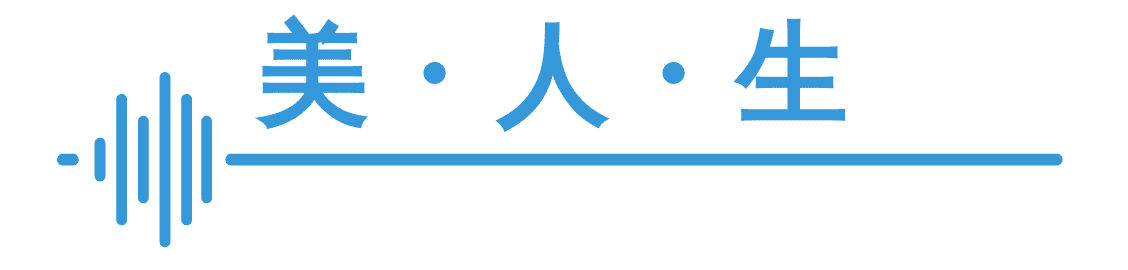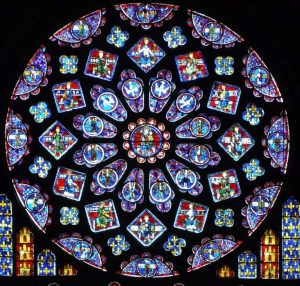西洋美術史 3 (初期ルネサンスから19世紀末まで:芸術と人間の500年)
西洋美術の歴史は、人類の思想や社会の変化と密接に結びついている。特に初期ルネサンスから19世紀末までの時代は、美術が宗教的表現から人間中心の探求へと進化し、多様なスタイルと主張が生まれた。本記事ではその流れを、代表的な芸術家と作品と共に解説する。
1. 初期ルネサンス(14世紀後半〜15世紀前半)
背景と特徴:
- フィレンツェを中心に、人文主義と古典復興が進展。
- 遠近法と写実表現の誕生。
代表芸術家と作品:
- ジョット・ディ・ボンドーネ
<聖フランシスコの嘆き>:感情と空間の導入。


- マサッチオ
<聖三位一体>:線遠近法の使用。

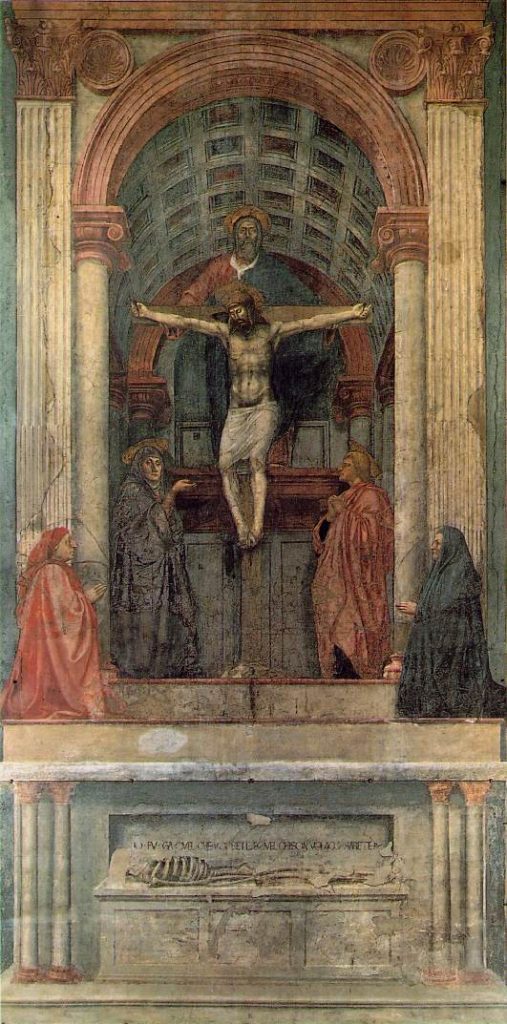
2. 盛期ルネサンス(15世紀後半〜16世紀前半)
背景と特徴:
- フィレンツェ、ローマ、ヴェネツィアに拠点が拡大。
- 古典美と宗教的主題の理想的融合。
三大巨匠:
- レオナルド・ダ・ヴィンチ
<最後の晩餐>、<モナ・リザ>:科学的観察と芸術の融合。
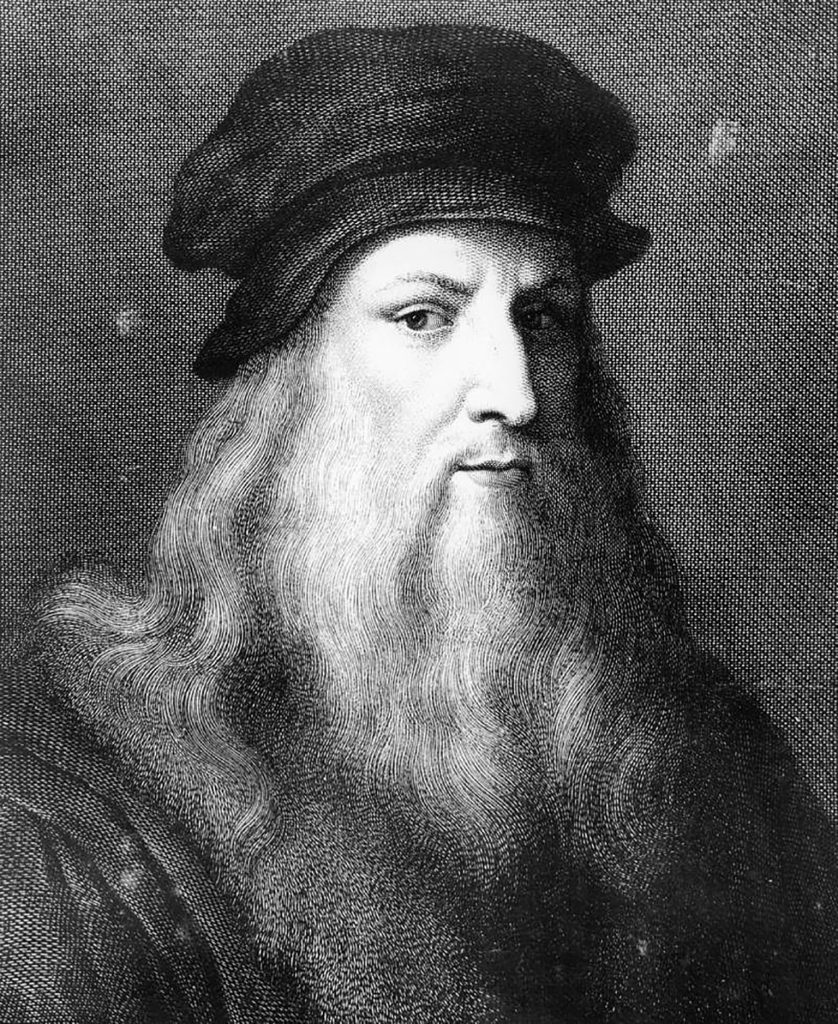
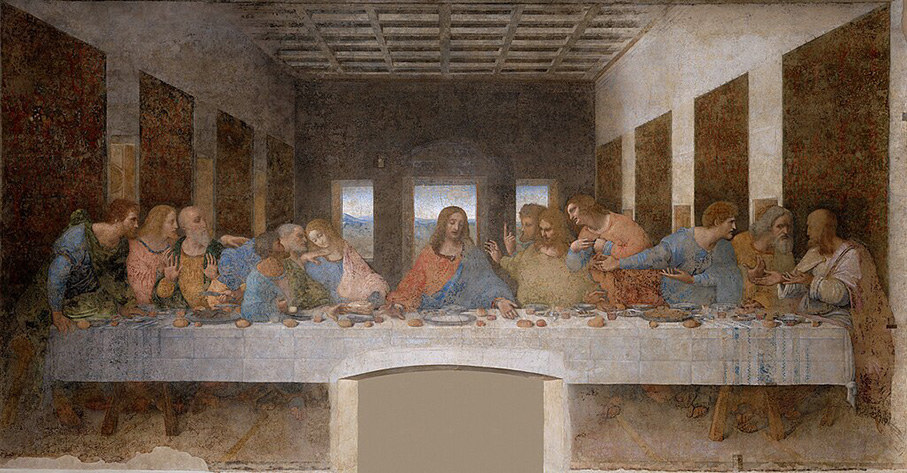

- ミケランジェロ
<ダヴィデ像>、<システィーナ礼拝堂天井画>:英雄的で緊張感のある人体。
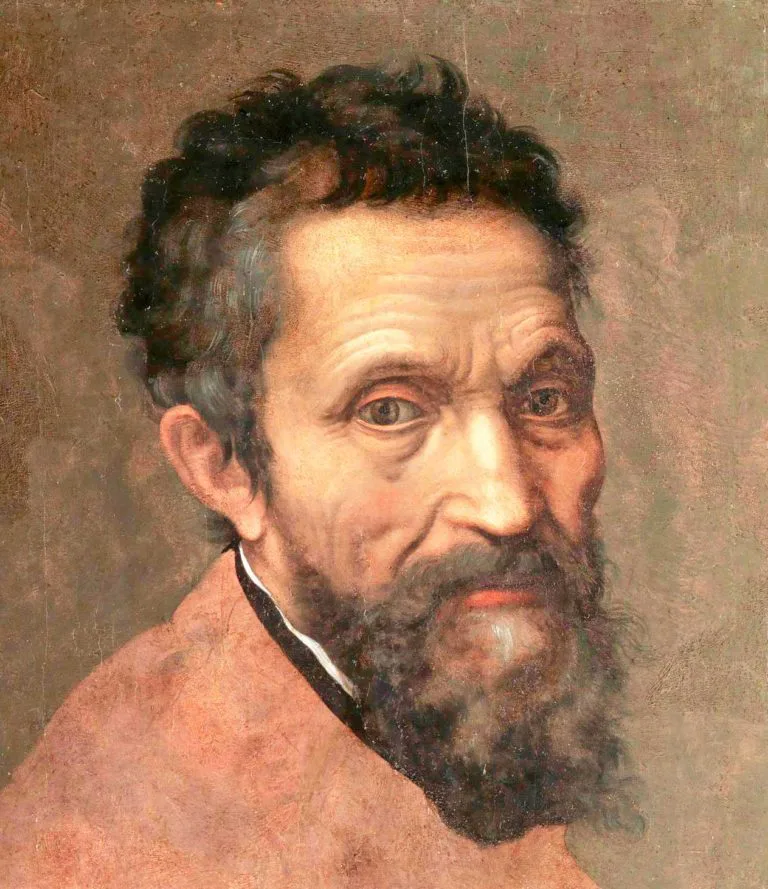
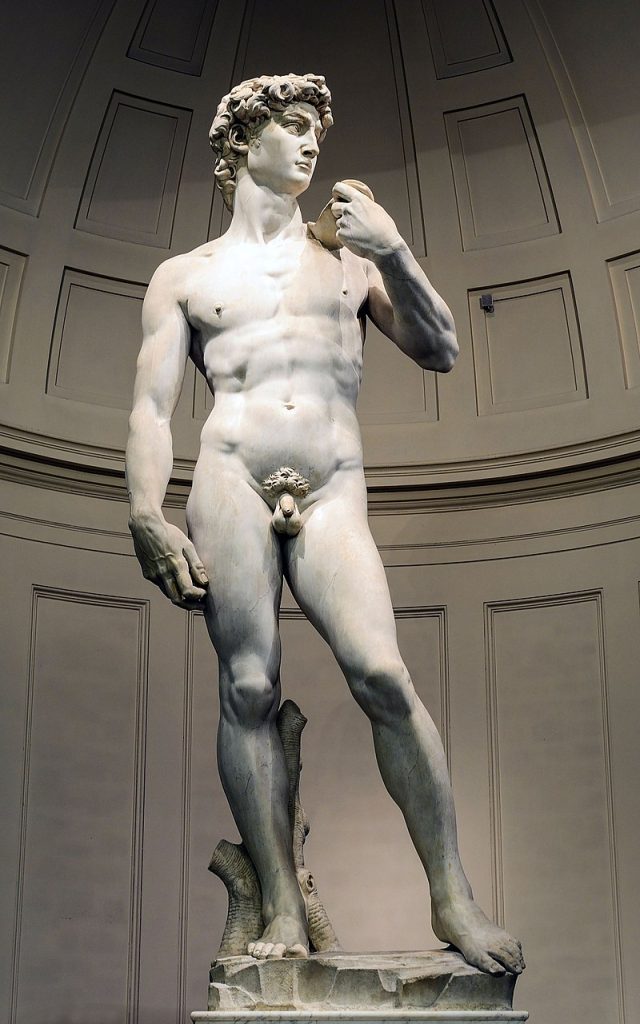


- ラファエロ
<アテネの学堂>:調和と理性の象徴。


3. マニエリスム(16世紀中頃〜後半)
背景と特徴:
- 盛期ルネサンスの完成形からの逸脱。
- 複雑で不自然な構図、誇張された表現。
代表芸術家と作品:
- パルミジャニーノ
<長い首の聖母>:人体の歪みによる幻想美。


- エル・グレコ
<オルガス伯爵の埋葬>:縦長の人物と霊的な光。
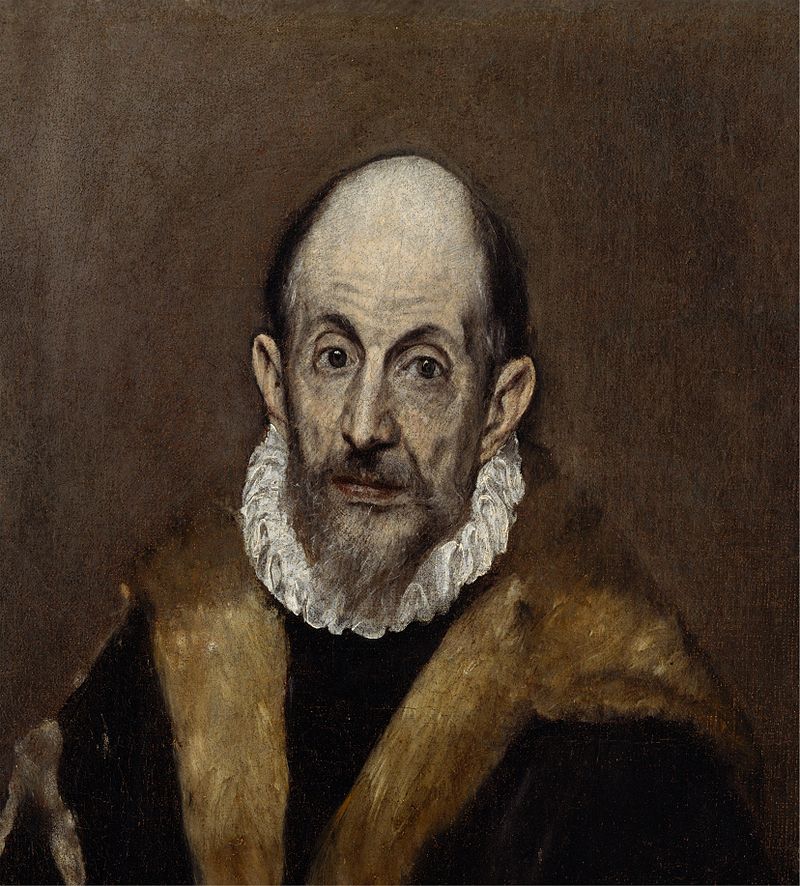

4. バロック(17世紀)
背景と特徴:
- 宗教改革への対抗としての感情表現。
- 王権や教会による美術の政治的活用。
代表芸術家と作品:
- カラヴァッジョ
<聖マタイの召命>:明暗対比(キアロスクーロ)と写実主義。
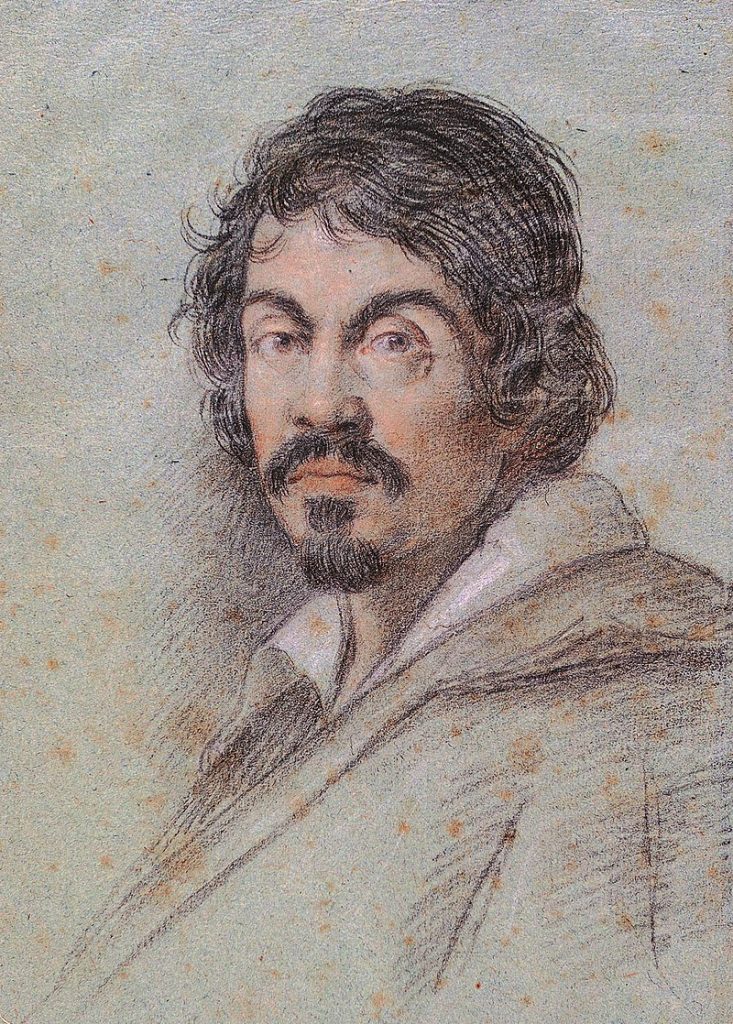

- ルーベンス
<キリスト降架>:ダイナミックな構図と動き。

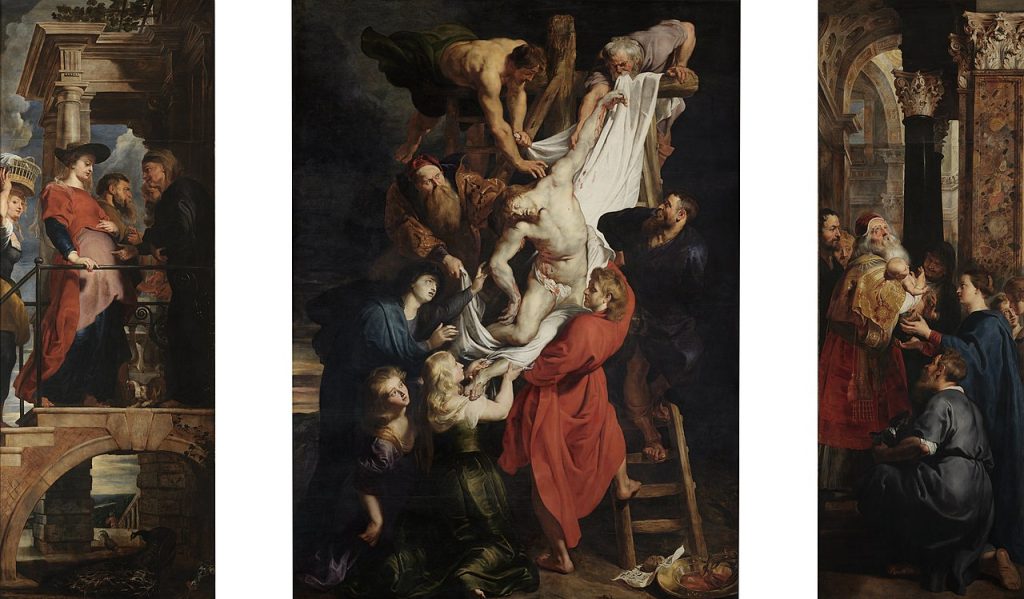
- ベラスケス
<ラス・メニーナス>:視線と空間操作の革新。
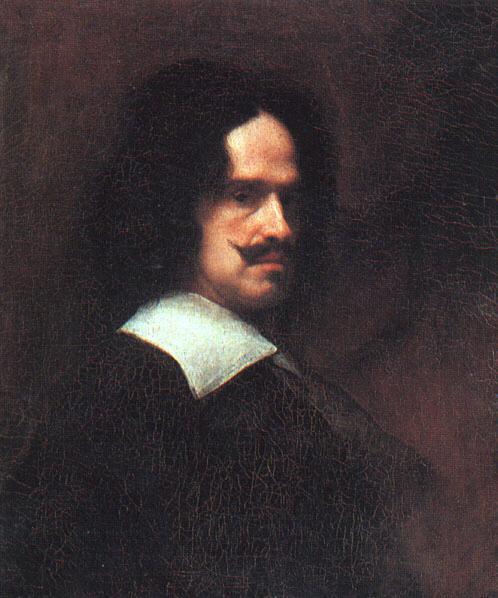

5. ロココ(18世紀前半)
背景と特徴:
- フランス宮廷文化に根ざした優雅さと軽快さ。
- 官能的で装飾的な雰囲気。
代表芸術家と作品:
- ヴァトー
<シテール島への巡礼>:雅宴画の先駆け。


- ブーシェ
<ポンパドゥール夫人>:洗練された官能美。


6. 新古典主義(18世紀後半〜19世紀初頭)
背景と特徴:
- フランス革命の道徳と理性の回帰。
- 古代ギリシャ・ローマへの傾倒。
代表芸術家と作品:
- ジャック=ルイ・ダヴィッド
<ホラティウス兄弟の誓い>、<マラーの死>:政治的かつ道徳的なテーマ。



7. ロマン主義(19世紀前半)
背景と特徴:
- 革命後の社会不安、個人主義の台頭。
- 感情、幻想、自然への没入。
代表芸術家と作品:
- ドラクロワ
<民衆を導く自由の女神>:色彩と自由の象徴。
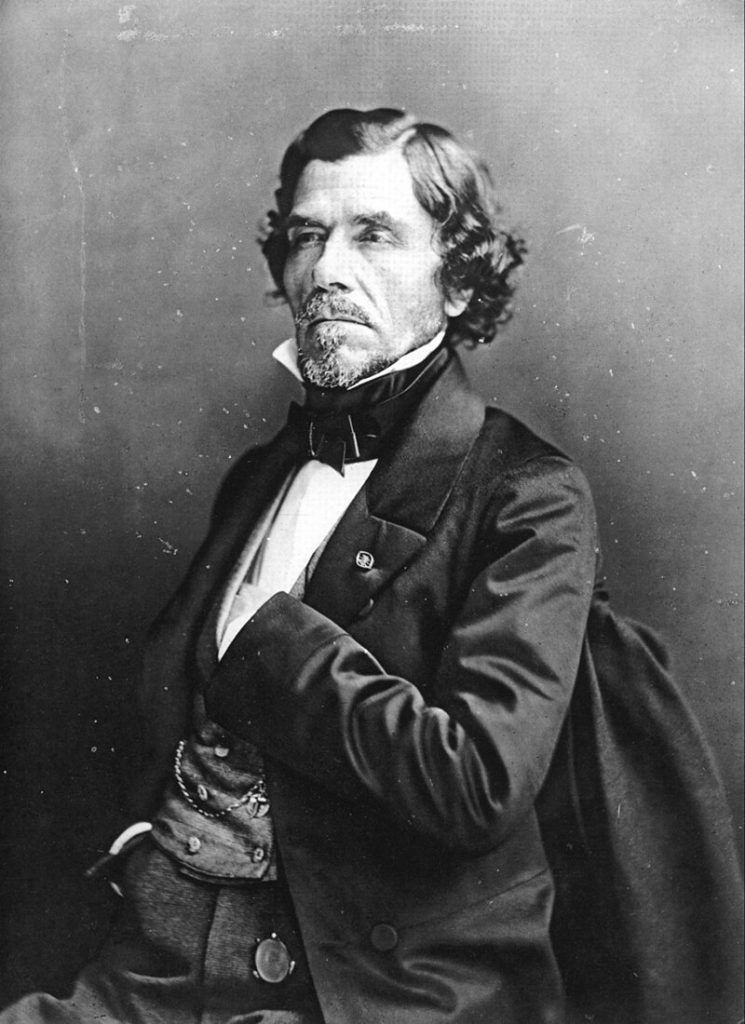

- フリードリヒ
<雲海の上の旅人>:精神性と自然への畏敬。


8. 写実主義(19世紀中頃)
背景と特徴:
- 産業革命後の社会現実へのまなざし。
- 理想化を排した日常の描写。
代表芸術家と作品:
- ギュスターヴ・クールベ
<石割人夫>:労働者階級の描写。
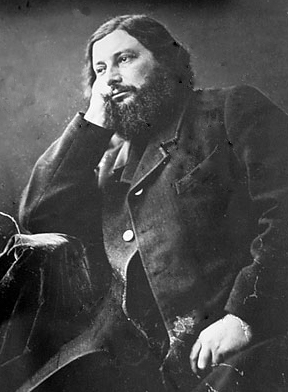
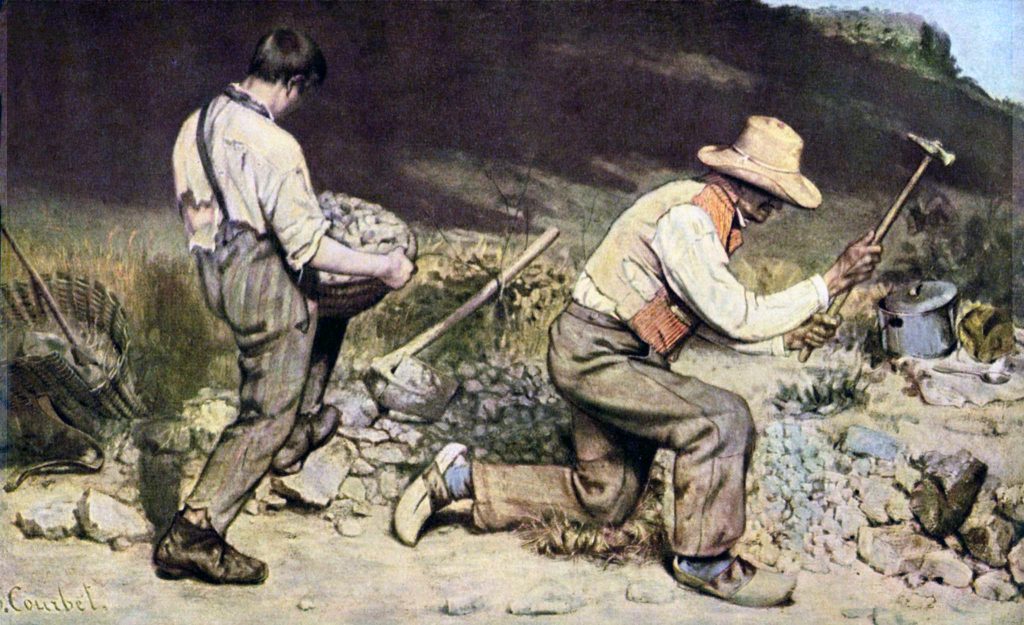
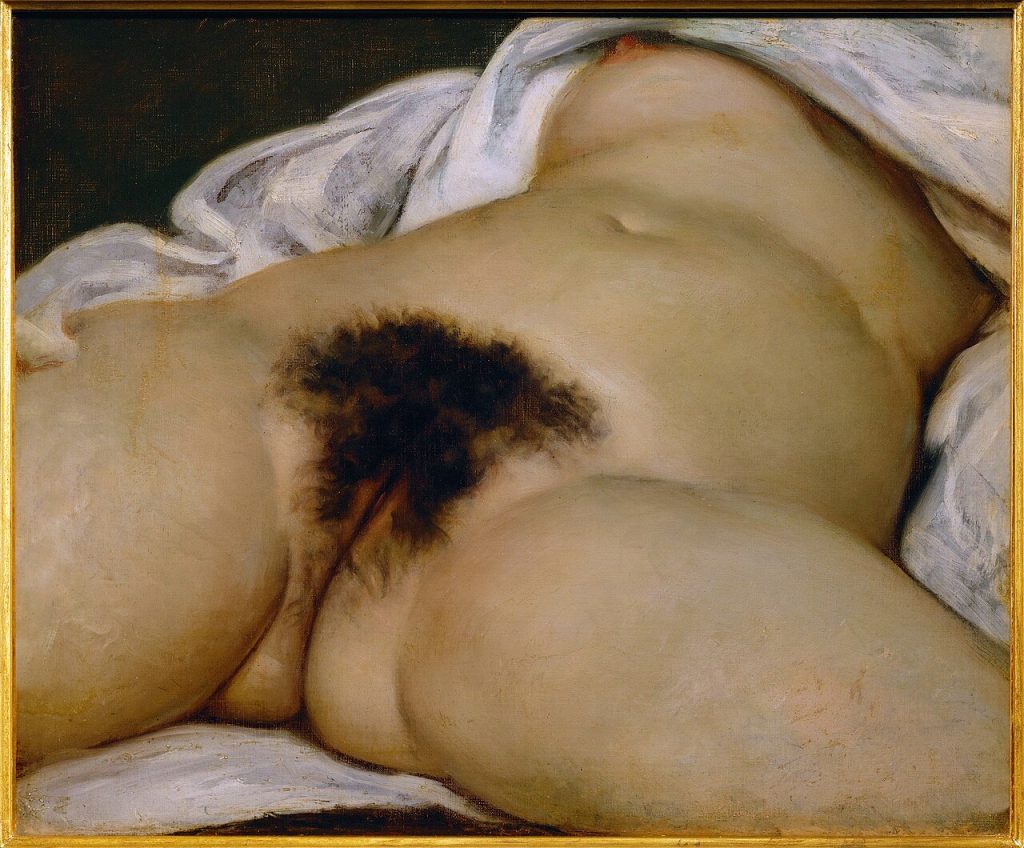
- ジャン=フランソワ・ミレー
<落穂拾い>、<晩鐘>:農民の静けさと尊厳。
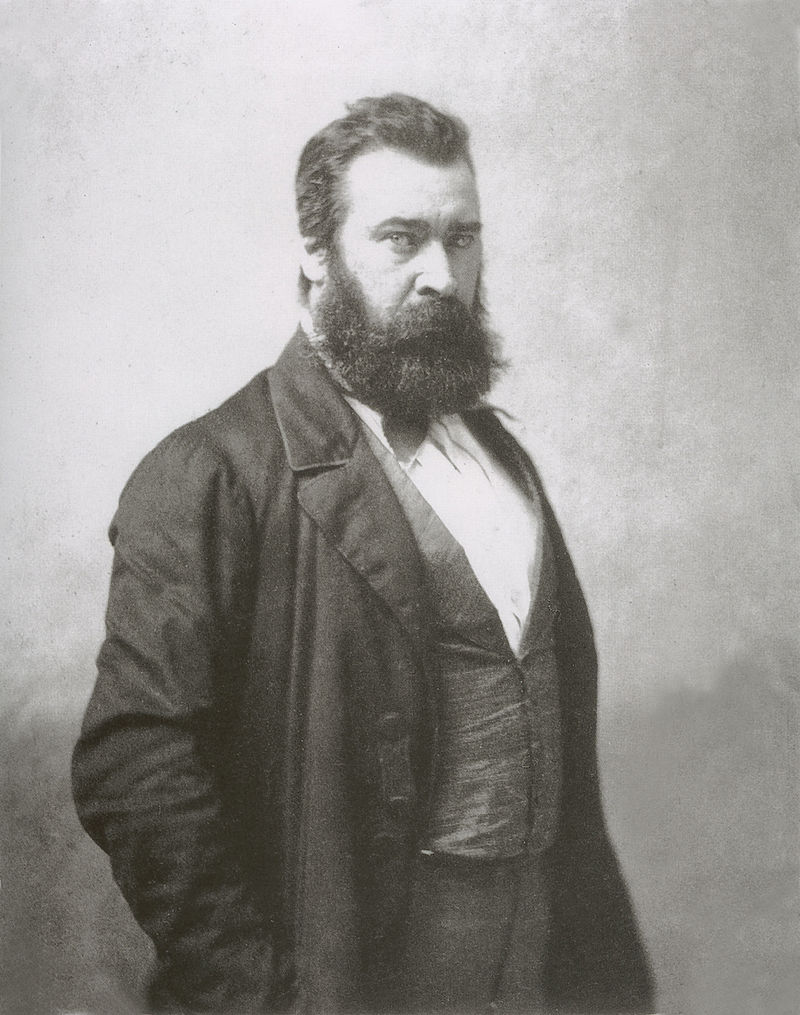


おわりに
500年にわたる西洋美術の流れは、ただのスタイルの変化ではなく、人間や社会の在り方そのものへの問いかけでもある。それぞれの時代に息づく美と思想を味わうことで、現代を生きる私たちにも深い洞察がもたらされるはずである。
 関連記事
関連記事
西洋美術史2(中世からルネサンス前夜まで:信仰と様式の変遷をたどる)